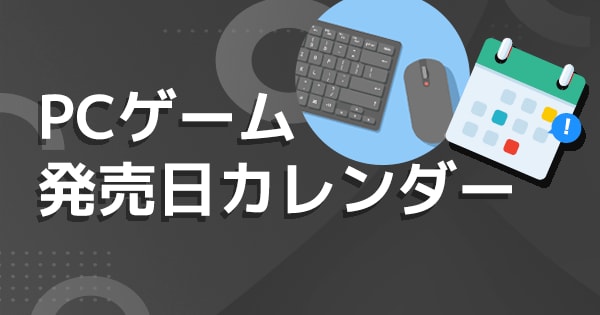※当記事のリンクはアフィリエイト広告を含みます。
13年ぶりに復活を遂げた忍者アクションゲーム『NINJA GAIDEN 4』。
コーエーテクモゲームスのTeam NINJAとプラチナゲームズがタッグを組んで開発した、「NINJA GAIDEN」シリーズの最新ナンバリングタイトルだ。2025年10月21日に発売予定となっている。
某日、プラチナゲームズのアートディレクター・西井 智子氏、リードコンポーザー・宮内 雅央氏、レベルデザイン&環境リード・阿部 雄大氏の3名にオンラインインタビューを敢行した。
本稿では、その内容をお届けする。
「逆境・残虐・変化」のコンセプトで開発されたシリーズ最新作

──『NINJA GAIDEN 4』はどのような方針で制作されたのでしょうか?
阿部:
コンセプトに関しては、ディレクターの中尾とよくすり合わせるところから始めました。
そこで出てきたコンセプトが「逆境・残虐・変化」。これが、「NINJA GAIDEN」シリーズにおける最もプリミティブな部分、面白さの源泉ではないかという結論に至りました。
数多の敵に囲まれる緊張感。それを突破した瞬間に一気に高まる興奮とアドレナリン、そして刺激的なビジュアル。
これら「NINJA GAIDEN」の魅力を最大限生かすには、どういったステージ構成にしたらいいのか、エネミーの構成にしたらいいのか、ビジュアルをどうすべきかなどを考えました。

▲レベルデザイン&環境リードの阿部 雄大氏
例えばステージでは、プレイヤーに逆境を感じさせるにはどう表現すべきかを考えました。
「ステージごとに大きな変化をつける」「高くそびえ立つ街並みで逆境を表す」、「どこまでも落ちていきそうな奈落を見せる」など、さまざまなアイデアが出ました。
さらに、プレイヤーに逆境感を感じさせる敵の配置や、逆境に次ぐ逆境を感じさせるシチュエーションの変化なども考えていき、アイデアを膨らませていった次第です。

──コンセプトとなるレベルデザインを先につくってから、アートワークや音楽などの要素を上乗せするといった順番でしょうか?
阿部:
正確に言うと、「キャッチボールしながら作っていった」が正解だと思っています。レベルデザイン側が放ったボールに対して、西井や宮内から「こういうアイデアはどうですか?」というようなボールが返ってくるイメージです。キャッチボールを繰り返して、アイデアをどんどん発展させていくフローでした。
西井:
先述した逆境の部分については、割と早いうちから常に情報が共有されていました。
そのコンセプトを前提として「あとはどうする?」という話だったので、「アート的にそれをやりたいんだったら、もうちょっとここを盛った方が良い「もっと脅威にしたいのであれば、もっと風を吹かせた方がいい」といった意見をいただきながら発展させることがほとんどでした。

▲アートディレクターの西井 智子氏
アート側としては、とにかくコンセプトを突き抜けさせるという方向性で進めていきました。なので、こちらからアイデアを出したというよりも、コンセプトの濃度を増やすことに注力していたと思います。
阿部:
そうですね。アート側の案を見せてもらって、私の方から「ここはもっとコントラスト高めのステージにしてほしい」など、とにかくピーキーな見た目になるような調整をお願いしました。
宮内:
僕の場合、ストーリーやステージ構成などが形づくられるのを見ながら「どんな曲を作ろうかな」とずっと考えていました。
できあがった楽曲をレベルデザイン側に見せて意見を聞いてもらったりして、クオリティを上げていく流れが基本です。「逆境・残虐・変化」をストーリー全体の流れで感じられるように、色々な曲を書かせていただきました。

▲リードコンポーザーの宮内 雅央氏
阿部:
僕が「こういうステージを作ったので、この曲でお願いします」と言おうとする前に、宮内から曲が送られてきたなんてこともあったんですよ(笑)。
彼が非常に意欲的に取り組んでくれたことを受けて、「こういう曲だったら、このタイミングに合わせてこんなビジュアルの変化があった方がいいだろう」とか、そういうキャッチボールも積極的に行いましたね。
──楽曲やアートなど全般的な話になりますが、「NINJA GAIDEN」シリーズの新たなナンバリングタイトルを作るうえで「ここは守りたい」「ここは過去作を超えたい」といったことはあったのでしょうか?
阿部:
本シリーズは最もピュアなアクションゲームと言っていいと思います。数々の難問を、ひとつひとつ切り抜けていく緊張感がとにかく最後まで続く。こういう最もプリミティブな部分に関しては絶対に守ろう、リスペクトしようと思いました。
根本を変えるというよりも、根本をさらにアップグレードさせる・盛るという形ですね。コンセプトのひとつである逆境を感じてもらえるよう、敵を強くしたり増やしたりしつつ、「鴉忍具」などプレイヤーができることもどんどん増やしていきました。
「元々あったものを120%楽しませるうえで、どういった改修が必要なのか?」という視点で、敵と戦うに値するメカニックを入れてみましたね。
本作ではステージが上下に広がっていて、今までよりも動いている感が強いというか、スピード感のある戦闘ができるようになっていると思います。ただ、シリーズ元来の戦闘の緊張感はそのまま生かしています。
──ステージのレベルデザインに関する質問ですが、ある程度固めたものを作ってからステージの開発を行ったのでしょうか?
阿部:
そうですね。まずデータを作る前に、全体のコンセプトの見通しのようなものを立てました。特に、チャプター1~3の序盤は、本作の面白さを最もベーシックに表現することにこだわっていました。我々が考えていた「逆境・残虐・変化」のコンセプトを感じられるような、気持ちよくなれるステージに仕上がっています。
──ちなみに、レベルデザインの構想はすぐに固まっていたのでしょうか。それとも、紆余曲折を経て生まれたのでしょうか?
阿部:
少し悩んだ部分もありましたが、基本的にはすぐ固まったと思っています。本シリーズ自体にプリミティブな良さがあると思うので、レベルデザイン上でトリッキーなことをするというよりも、もっと力強くストレートに作ってしまっても問題ないという考え方でした。
そういった考え方に対して、どれぐらいケレン味を入れられるのかといったところで我々の中でも調整はありましたが、難航したというほどでは全然なく、比較的ストレートに仕上がりました。
──敵の配置もレベルデザインに含まれているのでしょうか?
阿部:
ステージ上の演出や敵の配置、景観などもレベルデザインに含まれています。あとは、「NINJA GAIDEN」らしいエッセンスを感じてもらえるように、過去作を彷彿とさせる部分も所々に込められていますね。

──難易度についてのこだわりを教えて下さい
阿部:
最もこだわったところは逆境の表現です。極限の歯ごたえ、もっと平たく言えば「めちゃくちゃ難しい」ところにこだわりました。
「すごく強い敵を倒しているぞ」「すごく難しいゲームを自分はクリアしているんだ」という感覚をどういう風に作るか。ただ、難しすぎて誰もクリアできない状況はどうしても作りたくなくて、我々としてはすごく難しいけれども間口が広いものを目指していました。
特に、「鵺の型」はこれまでのシリーズにはなかった、ケレン味のある一発逆転のメカニクスだと思っていて、プレイヤー側が強くなれる部分かと思われます。難易度的に上がってはいるのですが、習熟はしやすく、すぐうまくなれるデザインになっています。
──先程、実際に本作を触ってみて、「そうそう、これぞNINJA GAIDENじゃん!」といった素朴な驚きがありました。
阿部:
ディレクターの中尾からも、「「NINJA GAIDEN」を作るんだ!」といったアピールが強くありましたね。我々もそのアピールを受け取って、何度も何度も過去作を確認しながら、「「NINJA GAIDEN」になっているのだろうか?」と本作の手触りを念入りにチェックしました。
実際に手に取っていただければ、「NINJA GAIDEN」らしさを感じられると思いますが、すでにそういった感想をいただけたので満足しております(笑)。
──クリア後に遊ぶことになるチャレンジミッションも、阿部さんが考えたのでしょうか?
阿部:
そうですね。ゲーム内に登場するステージはすべて監修しています。
チャレンジミッションなど、クリア後に遊ぶものに関しては、本編よりさらに「殺しに行こう(笑)」という風に最初から考えていました。
チャレンジミッションはとにかく難しい内容に仕上がっているため、中尾も僕もプレイしながらブチ切れるという(笑)激しい開発になるぐらい、突き詰めた難易度になっています。
めちゃくちゃ頑張ったらちゃんとクリアできるところは担保していますので、そこはご安心ください(笑)。
開発者が語る『NINJA GAIDEN 4』の魅力とは

──本作の世界観について、今まで以上にサイバーチックな印象がありました。世界観のテイストが変わった経緯についてお聞かせください。
阿部:
発想の源としては、「『NINJA GAIDEN 2』から10年経ったあとの世界を発展させてみたらどうなるのか?」「シリーズの正当進化として、世界観の延長線を伸ばしてみたらどうなるのか?」といったところからスタートしています。
ハチャメチャな世界観をさらに拡大解釈した結果、よりピーキーな世界観に仕上がった感じですね。
──サイバーパンク風のステージがある一方で、レトロでコミカルなステージも見受けられました。妖怪をモチーフにした「妖魔」もコミカルでしたが、どのような理由であの世界観を作り上げたのか教えてください。
西井:
妖魔に関しては、「NINJA GAIDEN」の世界観の延長である背景を踏まえつつ、日本の土地に根付いたネタを引っ張ってきて、さらに発展させた敵が必要だと思いました。
そこで、“妖怪”というモチーフにした妖魔が生まれたというわけです。「このステージでこういう敵を出したい」と考えた際、妖怪ならうまくマッチするかもしれないといった発想になりますね。

──本作では、過去作以上にゴア表現が強まったように感じました。ゴア表現を描くうえで、特に工夫された部分をお聞かせください。
西井:
ゴア表現については、少なくとも過去作より見劣りするのだけは絶対に避けたいと思っていました。先程の世界観と同じく、順当な積み重ねといいますか、延長線上にある進化をベースとして意識していたところでもあります。
本作の主人公である「ヤクモ」は、「血楔忍術(けっせつにんじゅつ)」という己の血を使うアクションを利用できます。

血の表現に注力した結果、思っていた以上に血がいっぱい出たり、ゴアが強かったりするといった印象に繋がったのではないかと考えています。
──本作の楽曲についてお伺いします。「NINJA GAIDEN」のエッセンスは受け継がれている一方、楽曲のイメージが変わった印象を受けました。楽曲の変化は意識して行ったのか、あるいはどういった意識から楽曲の方向性を見出したのかをお教えいただきたいです。
宮内:
13年ぶりのナンバリングタイトルということもあり、主人公の見た目やロケーション、時代設定などが今までと大きく異なります。そういった変化にならって、楽曲の方もアップデートしています。
楽曲をアップデートするうえで、プラチナゲームズが元から持っている、勢いのある雰囲気を上乗せしたいという考えも理由のひとつです。
たとえば、本作の目玉となるボス戦は盛り上がる楽曲を、他の部分では幅広いジャンルの楽曲を制作してみました。
曲の雰囲気は変わりましたが、「NINJA GAIDEN」という枠から出ないようにコントロールしています。楽曲も含めて、進化した「NINJA GAIDEN」を体感していただけるのではないかと思っております。
──試遊したチャプターには、レールの上を走るスピード感のある場面がありました。製品版には、ほかにも爽快感のあるギミックがあったりするのでしょうか?
阿部:
本作では緊張感のある戦闘と戦闘の間に、爽快感あふれるレールの場面などを挟んでいて、より長く新鮮な気持ちで戦闘を楽しめるようにしています。
詳しくは製品版で……ということで(笑)。

──試遊してみて、スピーディーな斬撃アクションの描写はプラチナゲームズさんらしさがあったかなと思いました。アクションの描写に関するこだわりについて教えて下さい。
西井:
ビジュアル面であれば、まず何かしらのアクションの表現を入れる場合に、過去作の挙動をコマ送りで研究してからアップグレードを行いました。
先ほどお話ししたアップグレードの話と流れは同じになりますが、VFXモーションセクションにおいても似たような流れを辿っています。

阿部:
私の方からも補足させていただくと、「NINJA GAIDEN」のアクションの気持ち良さはとにかく"緩急"という言葉に尽きると思います。たとえば、「滅却(欠損した敵にトドメを刺すアクション)」する時に、敵に寄って止まってズバッと斬るキビキビした動きとか、滅却の瞬間にカメラがググっと寄る感覚とかですね。
最初は、過去作を再現しようというところから始めようと思いました。思い出の中にある「NINJA GAIDEN」と滅却時の緩急などを再現していったのですが、実物と見比べてみると当初よりも激しいものになっていました。
なので、「過去作はこうだったよね」という感覚をイマドキ風に再現したら、本作ぐらいのものに仕上がっていたというニュアンスですかね。
そして緩急の最頂点となるものが、「血殺(けっさつ)」と呼ばれるアクションです。血殺が決まった際に画面の色ごと変えて、動きを止めて、気持ちのいい絵を一緒に見せる、というところが本作のウリになると思います。

宮内:
斬った時の爽快感でいえば、血殺は一番ド派手な音がポイントになっていると思います。戦闘の中でも音のメリハリがつくように、爽快感がかなり付加されていると思います。
──チャプター3までプレイした中で、白い敵のデザインがとても印象的でした。全体を通して、本作は“白”に重点を置いているのでしょうか?
阿部:
発想の源は主人公が黒で、それに相対するものが白というセッティングから始まっています。なかなか汚れた世界観なので、白い敵は目立ってよかったと思いますね。
あと、主人公の孤立感みたいなものを示すために大胆な色分けをしたところが、白と黒のスタートですかね。

西井:
プレイヤーと敵とのコントラストが発想の源でもありますし、斬って血がいっぱい出るゲームだから白い方がより目立つだろうなと。
比較的クリーンなイメージがある白を、プレイヤーの手でぐちゃぐちゃにする気持ちよさも味わえるのかなと(笑)。その気持ちよさを体感してもらうべく、序盤に白い敵を登場させたところもあります。
白だけだとさすがに変化がなさすぎるので、序盤は白い敵がかなり目立っているかもしれませんが、もちろん後半になるにつれて違う色の敵も登場します。
──試遊では2種類の武器が使えますが、どういったコンセプトで武器を作られたのでしょうか?
阿部:
武器について最初に考えたことが2つあります。1つは、僕らの考える戦闘の偏りをうまいこと均等に分けていったら、本作の武器の種類になった感じです。
もう1つは、ヤクモとリュウ・ハヤブサとの対比を作りたかったことが大きいですね。リュウ・ハヤブサは力強くてストレートなイメージなんですが、ヤクモはもっとテクニカルに戦う印象を与えたいと考えていました。
そこから生まれたのが、変化する武器だったり、いくつかの武器を切り替えながら戦ったりできるコンセプトになります。

西井:
それぞれの個性がちゃんと立つような武器のデザインを選びましたね。「リュウ・ハヤブサはめちゃくちゃ強くてカッコいい存在なので強い武器が良い」とか「ヤクモは小柄なので、そのギャップを引き立たせるためにジェットをつけてみよう」といった案がありました。
──ドリルの武器が出てきたときはかなり驚きましたが、「NINJA GAIDEN」的に制限はなかったのでしょうか?
阿部:
特殊な技を使って大きな武器を生成するのは、本作からの新要素になります。そういった新要素はなるべく突き抜けようといった意識で始まったかなと思います。
「NINJA GAIDEN」らしさの基準については、西井とやり取りしながら限界まで突き抜けていった感じですね。
西井:
基準は最初に定めたわけではないのですが、「シリーズの象徴である残虐性が出ない武器はダメ」とか「「NINJA GAIDEN」的に気持ちいいところが削がれる武器はダメ」みたいなものは根底にはありました。
まずは「NINJA GAIDEN」としての気持ちよさを守るところで一旦案を出してみて、それでやりすぎたら少しだけ調整し、あとはとにかく突き抜けていきました。先ほど述べた“濃度を増す”部分は、ここでも割と意識して選んでいましたね。
──最高難易度の「MASTER NINJA」を少し触らせていただきましたが、一発の攻撃で体力が8割ぐらい削られてしまい、難しいと感じました。開発側ではどれぐらいの割合でクリアできましたか?
阿部:
僕ももちろんすべて通しプレイをしているのですが、MASTER NINJAのデバッグが一番大変でした(笑)。デバッグできる人も限られるぐらいに。
正確な割合はわかりませんが、クリアはできます。過去作でMASTER NINJAをやり込んだ人もぜひやってほしいなと。
ニンジャガ愛満載の開発秘話「開発は大変でしたが楽しかったです」

──皆さんのお仕事の中で大切にしていることと、本作でそれがどういう風に活かされたのかをお伺いできればと思います。
宮内:
これはいつも思っていることですが、僕はあくまでも作曲側なので、ゲームにおける曲や音は"お化粧"に例えています。ゲームの下地があるうえに感情面での表現を上乗せする、いわばお化粧をする感覚を強く思っていますね。
本作でも色々な顔(曲)を作らせてもらいましたが、「プレイヤーを最後まで飽きさせず、とにかく楽しませること」をかなり念頭に置いていました。
本作は近現代の舞台設定なので、新しさやカッコよさがぱっと伝わるような曲を用意しようかなと。ジャンルを問わず、カッコいい曲をかき集めたらどうなるんだろうと個人的な意欲もありましたが、それによって「NINJA GAIDEN」らしいカオス感を表現できたと思います。
阿部:
レベルデザインの仕事は、料理のコースを考えることだと思っています。それぞれの素材や料理を、どの順番で出せば旨味が出るのかを考えるイメージですね。
どの順番でステージを見せれば本作のコンセプトを強調できるのか。それぞれの要素が最も映える配置を考えることを一番大事にしていますね。
西井:
アートに関しては、見た目がポンと入ってくるところなので、直感的であったりアーティスティックであったりとか独創的と思われがちですが、実際のところは翻訳家だと思っています。
まずは、企画としてのコンセプトを視覚的に分かりやすくすること。要はデザインとしてのアウトプットが大事なんですね。見た目がかっこいいのが大事ではなく、「何を表現したくてこのデザインになっているか?」といった変換作業がミソだと思っています。
そのうえで大切なのが、それぞれのスタッフがやりたいことを聞き取って理解することです。アートは基本的に翻訳できない言語だと思っているので、直感的に分からないといけません。とにかく相手へ伝える部分がちゃんと通るようにするところを意識してやっています。
これが結局どういう風にアウトプットされたかと言うと、「パッと見で敵が白い、見やすい」「強そうな敵がいる」「ステージとして圧迫感があるからなんか大変そうなところだな」と、言葉のいらない言語になると思います。そういったところを重要視して、仕事としてアウトプットをしておりました。

──本作の開発で、苦労されたエピソードはありますか?
西井:
中尾さんのチェックで「なんか違うんだよな。過去作のあの感じをもうちょっと出したいんだよな」といった話がありましたね(笑)。
中尾さんの強いこだわりについていくのが大変でしたけど、こっちも楽しくなってきて色々と調整するのが面白かったですね(笑)。
阿部:
私は、「NINJA GAIDEN」らしい難易度を作るところに苦労しましたね。ハードなアクションゲームであることがウリですが、「NINJA GAIDEN」は3以降しばらく休眠していました。
他に参考にできるものがなかったので、「NINJA GAIDEN」を参考にしながらさらに難しい「NINJA GAIDEN」を作る。序盤から後半に行くにつれて、より巨大な脅威を作っていく。
本作の突き抜けた脅威感を表現する部分は、連日連夜みんなで話し合った覚えがあります。
宮内:
言葉にできない「NINJA GAIDEN」らしさを追求することもそうですが、僕の場合はシンプルに曲でしたね。
多彩な曲を手がけることが作曲家の本質ではありますが、とにかく作曲が大変でしたね。でも楽しくやらせていただけました。
──それぞれ大変な部分があったと思いますが、全体的に振り返ってみていかがでしたか?
阿部:
楽しかったです。本作は突き抜けたゲームだと思いますので、我々は興奮しながら作っていましたね(笑)。
──プラチナゲームズさんは他社との関わりが結構あると思いますが、「NINJA GAIDEN」を研究するにあたって、Team NINJAさんとの違いを感じたことはありましたか?
阿部:
やっぱり「ケレン味大好き」というところがプラチナゲームズの特徴なので、そこがTeam NINJAさんとの違いだと思っています。
宮内:
曲に関しては、やっぱりゲームがサントラの雰囲気を決めると言いますか、ゲームの本質に引っ張られるところで、好き勝手なものを作れたところは大きいと思います。
それができたのも「NINJA GAIDEN」というIPのおかげかなと。
西井:
プラチナゲームズ的に問題ないと思って提出したら、より洗練されたものを求められることがしばしばありました。その際、Team NINJAさんのゲーム制作におけるラインを感じました。
他のチームのこだわりがフィードバックという形で、しかも目に見えた形で返ってきたので、Team NINJAさんのクオリティの出し方を学ぶことができました。
──皆さんの「NINJA GAIDEN」の好きなポイントをお聞かせいただいてもよろしいでしょうか?
西井:
緊張感があるとか難しいとかはありますが、個人的にはリュウ・ハヤブサが大真面目なところがすごくいいなと(笑)。
「NINJA GAIDEN」は突飛な世界観や突き抜けたシチュエーションが魅力なのですが、そんな中でもリュウ・ハヤブサはストイックに、真面目に突き進んでいく印象を受けましたね。

阿部:
私は、とにかくピュアなゲームであるところが好きですね。
「アクションにすべてのリソースをつぎ込み、極限まで考え抜いてみたらどうなるんだろう?」というようなことを限界までやっているシリーズだと思っていて、それが唯一無二の手触りを作り出しているのではないかと。
宮内:
僕は、リュウ・ハヤブサを演じていた堀 秀行さんのアイコニックな演技とか声とかがすごく耳に残っています。アクションを突き詰めて体験させようとするゲーム性も、唯一無二だと思いますね。
──ありがとうございました。
その他の新作ゲームもチェック!
©2025 コーエーテクモゲームス. Team NINJA All rights reserved.
NINJA GAIDEN, and the Team NINJA logo are trademarks of KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
© PlatinumGames Inc.
今後発売の注目作をピックアップ!
2026/01/29 発売
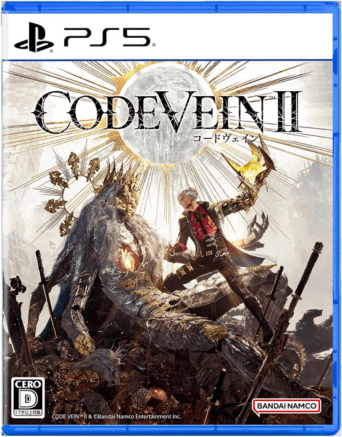
CODE VEIN II
5,272円(税抜) 2
2025/12/04 発売
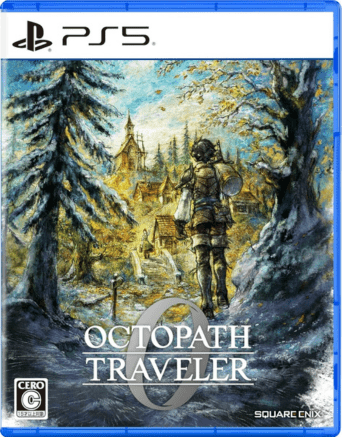
/PC/PS5/Xbox
オクトパストラベラー0
6,980円(税抜) 3
2025/11/14発売
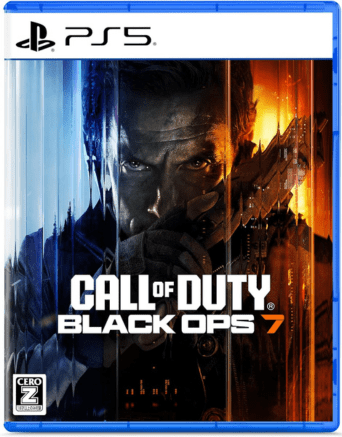
/Xbox
Call of Duty: Black Ops 7
8,909円(税抜)